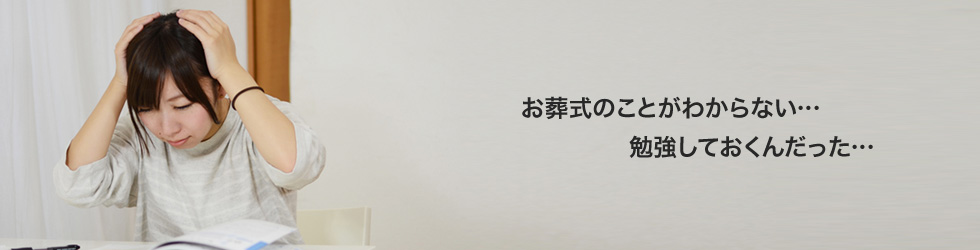開眼供養とは仏壇を単なる位牌を納める箱から、寺院とする為には僧侶に開眼供養(かいげんくよう)をしていただく必要があります。開眼供養を行わないと故人の魂を受け入れることができませんので、これは決まっていることとお考えください。仏壇がただの箱で終わってしまいます。
2013/10/17
2013/10/03
併修とは複数の法事・法要を同時に行うこと
レアなケースかもしれませんが、父の三回忌と祖母の十三回忌などといった具合に家族の法事・法要が重なることがあります。そうなると施主側も参列者側も時間や体力、経済的に負担が掛かってしまいます。それを避ける為に法事・法要を同時に行うのが併修となります。遺族の理解が得られるのであれば、最初から併修を考える必要はありません。
2013/09/21
法事・法要をしっかりと準備する[菩提寺なし]
法事・法要が初めての場合は段取りがわからないものです。初めてということは初七日法要か四十九日法要が該当するかと思いますが、基本的に準備することは同じになりますので、どの法要においても共通のものとお考えください。法要だからといって準備を怠らないようにしましょう。菩提寺がない場合を想定しております。
2013/09/11
仏式の年忌法要一覧[一周忌は必ず行う]
仏式の年忌法要は計10回存在していますが、一般的に行うのは一周忌法要、三回忌法要、三十三回忌法要の3種類となっています。一周忌までで終わらせるご家庭も見受けられますが、年を重ねるうちにどうしても記憶が薄れていくものですので、故人を偲ぶ意味でも年忌法要はできるだけ行ってあげるべきだというのは個人的な意見です。
2013/07/22
各種法事・法要の会食までの一般的な流れ
一般的な法事・法要の流れをご紹介します。ただ、法事・法要の規模の大きさにもよりけりで、お付き合いの長い菩提寺とご家族だけで行う場合はこういった流れを堅苦しくする必要もないかと思います。特に施主の挨拶は省略されることがほとんどですが、内容に関してはこの通りで間違いないでしょう。
2013/07/19
仏式の法事・法要の一覧[忌日法要・追悼法要]
仏式の法事・法要には細かすぎるぐらいの種類が存在しています。忌日法要(追悼法要)は計8回存在しており、全ての忌日法要を行うと大変なことになってしまいます。全て行うことを止めたりはしませんが、決して全て行う必要はありませんし、行わかったからといって何かがある訳ではありませんのでご安心ください。